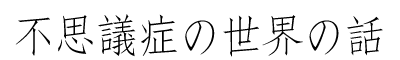
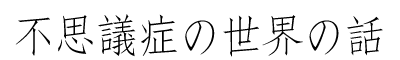
- 2. 3~4歳期
- 3. 幼稚園期
- 8. 高校受験期
生まれた時は若干小さかったくらい。出産も全く順調で、一切問題ありませんでした。
それ以降、首が座る・発語・這う・立つ・歩く…などは全て本等に書かれているスケジュール通り。全く普通でした。
まだ寝ているだけの時も、覗き込むと目が合うし表情は豊かで、笑わせるとよく笑い、ごく普通の赤ん坊でした。
発語が一般的な時期であり、その後も口真似、つまりおうむ返しで語彙が増えていったのですが、なぜか、お茶が飲みたいときに「おちゃ」という言葉を発する以外、自分の意志や気持ちを言葉にすることはなく、いつまでもおうむ返しの言葉しかないことに、少し違和感を感じ始めました。
3歳前になると、おうむ返し以外の言葉がないことがはっきりし、通っていた幼児教室の先生からも年齢相応に精神年齢が達していないことを指摘されました。
当時は「ビデオ症候群」ということが言われたり、5歳位まで発語しない言葉遅れもままある、というような話を聞き、そんなものかも、と多少気楽に考えたい気持ちもあって考えていました。
地域の3歳児検診の前に、ついに医療機関に連れて行き、診て頂きました。その時は特に明確な判定はされず、いわば親のカウンセリングの状態でした。「定期的に診て行きましょう」ということで帰ってきました。
後になって考えると、この時に「自閉症」とか「知的障害につながる」とか告げられなかったことが、我々親にとって不要なショックや絶望を感じずに済んだ、という意味で非常に重要な意味を持ちました。また、育て方次第でどのようになるか未知数ということが、できるだけのことをやろう、というモチベーションにもなりました。
これ以降、この医療機関からご紹介いただいた様々な療育機関等に連れて行ったりして、本格的に「障がい」に取り組むことになりました。
← もくじに戻る
(会話としての)言葉がない状態なので、幼稚園の年少組に入れるのは無理と判断して、療育機関に連れて行ったりしていました。
相変わらず言葉はおうむ返し以外はありません。あるクリニックの勧めで大学病院に診てもらいに行きました。その結果、脳のレントゲン写真や脳波には全く異常は見られないものの、診断結果としては「中機能自閉症」と告げられました。
また、同時期に受けた知能検査ではIQ70前後、ということで「知的障がい有無の境界」というふうに言われました。
ただ、自閉症というには、よく笑って表情が豊かであること、こちらが見て不思議なものに執着する(例えば流水の様子を長時間楽しげに見つめている、などのような)ことはあるものの、典型的な症状としてよく言われる「ルーチンにこだわる」とか「すぐパニックに陥る」とかが見られないことなどから、この診断結果に対してあまりピンとこなかった、というのが本音です。
もちろん典型的な状況を示すところも多々ありました。例えば、先の「流水」のような興味あるものを見つめているときは手のひらをはばたくようにひらひら動かしていたり、何かを考えながら一人でほほえみを浮かべて体を前後にゆすっていたり、全く聞いたことの無い擬音語擬態語のような言葉を独り言で言っていたり、というようなことです。
とはいえ、ただ知的に遅れていくのを親として黙って見ているのにしのびず、いろいろ幼児教室的なところへ連れて行って学習らしきことをさせると、記憶力の面では思いの外能力を発揮して見せたりしました。
← もくじに戻る
(おうむ返し以上の)言葉の無い息子を快く受け入れて下さるというクリスチャン系の私立幼稚園を妻が見つけてきました。
この幼稚園は本当にすばらしく、子供第一主義を貫いており、子供たちをほとんど叱ることなく良い方向に導いていく手法を持っておられました。
また、子供たちの自主性、問題解決能力を高めること、お互いの協力と共感を大切にすることなど、園児たちを実に上手に子供なりの高い人格を持たせるよう指導されている幼稚園でした。
そして、何より「子供たちが必要とするものは全て提供してあげていいのです」という考えの下、息子の場合抱かれていれば安心して大人しく全てを受け入れることを見抜き、幼稚園二年間ほぼずっと担当の先生に抱いていただいて過ごしました。
園児たちも息子の「普通でないところ」を「普通に」受け入れ、仲間として徹底サポートしてくれたため、息子は「自閉症」と診断されたにしては人懐こく、人と関わることが決して嫌いではない人間になりました。もちろん「自閉症」と診断された人間ですから、普通に見ても「われ関せず」のように見えますし、過度に介入されるとパニックになって噛みついたり、というような過剰な反応を示しますが、園児たちもそれを心得ていて、あるときは自由に放っておき、あるときは息子にパニックを起こさせないようにいろいろ手助けしてくれる形で距離を保ちながら付き合ってくれたのです。
息子の社会性がある程度発達できたのは、この幼稚園時代のお蔭であると、今でも私は考えています。
← もくじに戻る
この時点で、まだおうむ返し以上の「会話」ができていませんでした。
いろいろ悩み、調べ、試しもしてみましたが、結局地域の公立小学校に入れるしか選択肢は残りませんでした。
しかし、案ずるより産むが易し、なのでしょうか、普通の公立の小学校が、結果から見ると唯一の選択肢であったとともに最高の選択肢であった、と今では思っています。
小学校入学時には、いやなものは「イヤ」というぐらいの反応ができるように働きかけ、多少そのようなコミュニケーションが生まれつつあったと記憶しています。
幼稚園時代に非常に順調だった状況を小学校にも詳細に説明し、可能な範囲で多少とも幼稚園時代に準じた扱いをしていただけるようお願いしました。こちらの期待以上の対応をしていただき、うまく小学校生活にエントリーすることができました。
小学校入学時に親が望んでいたことは、周りの生徒さんたちと一緒に机に座って時間を過ごすこと。教壇の先生が教室のみんなに話すことを自分に向けて話されることと認識できない息子にとって、授業で学習してくることは無理だと思ったので、学校に対しても学習することまでは期待していないと伝えました。
もし、授業に参加しない状況で机に座っているだけがあまりに苦痛なようであれば支援学級の方に連れ出していただければ、と学校にはお願いしたのですが、ほとんどは逆に支援学級の先生が授業にアテンドしていただき、予想外に勉強の方も何とか学校でしてくるようになりはじめました。
これも嬉しい誤算でした。
← もくじに戻る
非常に熱心な担任と支援学級の先生に恵まれ、学習面も精神年齢的にも大きく成長しました。
なんと、小学校2年生にもなって男性の先生の膝に乗せてもらって勉強を教えていただいたこともあったようです。
相変わらず、教壇から生徒全体に話しかける先生の言葉は指示としては受け取れていませんでした(ただ、授業としては聞いているところもあって、知識・記憶としては蓄積していっている気配もありました)が、名前を呼びかけて個別に指示すると聞けるようになりはじめたので、先生にも、指示に関してはできるだけ声掛けをお願いしました。それを徹底していただいたようで、3年生くらいになると、かなり普通に近い形で授業に参加できるようになり始め、テストの成績なども上がりだして、記憶力に頼るような科目は上位になるくらいになりはじめました。
担任の先生との相性にもよるのでしょうが、4年生になると、一応学校の授業で勉強してくるようになり、成績もあがり、担任の先生からは「ほとんど問題はないです」と言っていただくに至りました。支援学級のサポートを受けることもめっきり減って、親としては「もしかするとこのまま健常児との境が消えていくのでは…」という期待すら膨らみました。
もっとも、日常の姿を見ている限りでは、精神年齢がまだ幼稚園児に達しないことや、自分の気持ちをうまく言葉にできないだけでなく言葉そのものをまだ決して自由に使いこなせるに至っていないこと、クラスメイトの顔や名前をほとんど覚えないことをはじめとした無数の欠落を持っていることはよく分かっていましたので、あくまで学校生活において、という限定つきでしたが。
海の生物採集やいろいろな地域のお祭り、模型エンジンなどさまざまなマニアの世界にはまりはじめたのもこの頃です。「強いこだわり」がこのようにマニアックな世界に向くのはこういう子供にとって決して悪いことではないと思い、親として精一杯これに付き合いました。
← もくじに戻る
順調すぎた4年生までと違い、小学校5年生は息子にとって最悪の1年となってしまいました。
担任の先生が、厳格な減点方式の発想の人であり、息子が4年生のときかなり普通に近づいたことが却って禍になったのか、息子に対して「普通にできるはず」という姿勢で圧力をかけてこられたのです。
3歳前に最初に診て頂いた心理士の先生から「このタイプの子は傍から見て普通に見えるようにふるまうのはとても努力が必要です。あまり普通にしろ普通にしろ、と追い詰めないでください。あまりプレッシャーがかかってパンクしてしまうと成長することに却ってマイナスになることがありますから。むしろ普通に見えるようふるまっていたら褒めてあげるようにしてください」というようなアドバイスをいただいていましたが、まさにその言葉通りのことが起こってしまったのです。
息子は授業中に床に転がってむずかったり、それまで素直すぎるくらい素直に先生や親の指示に従っていたのに、指示される度にパニックのようになって何かをすることがいちいちすすまなくなってしまいました。勉強に対しても全く興味を失い、成績も下がり、また支援学級の助けを借りることが多くなってしまいました。ところが、その担任の先生は、支援学級の先生が授業で息子にアテンドすることすらやんわり拒否するありさまでした。
学校の慣例では担任の先生は6年生もそのまま持ち上がりになる、ということだったので、たまりかねた私は学校へ行き、状況を説明して対応を求めました。結果的に、6年生では2・3年生のとき担任をしていただいた先生に担任をしていただきました。
6年生になり担任の先生が変わると、息子は驚くほど元気になり、4年生の時を超えて、授業への参加もできるようになり成績も元に戻る以上の状態となりました。支援学級にもほとんどサポートしていただかなくても良いまでに至りました。それを見ると、5年生の1年間も必要な試練だったのかな、という気がしたほどです。
← もくじに戻る
小学校入学時と同じように悩みましたが、やはり結果は同じで地域の公立中学校に入れるという選択肢しかありませんでした。そして、それが結果的にベストであったことも小学校入学時と同じでした。
中学校の場合担任の先生の影響と言うのは小学校ほど強くありません。
息子が入学した中学校には非常に熱心な支援学級の先生がおられ、3年間を通して徹底して息子のサポートをしてくださいました。おかげさまで、息子は中学の3年間滞りなく成長を見せてくれました。
もともと運動・スポーツ関係は全く興味がなく、障がいと関連性があるような気がするのですが、体を動かすことが極端に不器用なため、体育はダメでしたが、それ以外の科目は成績も上位を保つようになりました。
意外だったのは、言葉がうまく使えないにも関わらず、英語や国語が最も得意な科目となったことです。その他、相変わらず記憶力が優れるため社会科関係は得意でした。
また、これも障がいが関わっているとは思うのですが、手先がおそろしく不器用なのですが、ビジュアル的な着想・発想はおもしろく、美術関係も比較的好成績でした。また、自閉症児の2割近くに絶対音感があると言われるらしいですが、音楽も好きな科目であったようです。
技術家庭科も、手先はおそろしく不器用なものの何かを作ることが好きで発想・着想がおもしろい作品をつくることと、記憶力が優れることを活かしてペーパーテストで点をとり、比較的良い成績をつけてもらっていました。
一方、頭の中の論理回路が完全に欠落しているため、記憶を使って適当にごまかせた小学校時代とは異なり、数学の成績は中学校の学年が進むとともに下がり続けました。理科の第1分野も同様です。
不思議なことに、理科の第1分野の内容的なことには非常に興味があるにも関わらず、論理的な組み立てが全くできないのです。物事の因果関係を口で説明するのと頭の中にその因果関係が図式化されることとは別問題のようです。
← もくじに戻る
そもそも、小学校入学時から、学校に行かせる目的は人間集団の中で生きていくことに慣れさせるため、と割り切っていましたので、勉強は家庭で教えるしかない、と考えてやってきました。
学校の授業すら受けてくることができない息子を塾などに行かせたところで意味がない事なので、息子にとって「学習」する場所は主に家庭、ということになっていました。
中学生になってもこの点は同じで、学習塾などへ行かせることはせずに親が勉強を教えていましたが、この段階になってあらためて息子の頭の中が一般の人とは違うことに驚かされることが多々ありました。
中学1~3年期にも書きましたように、国語関係や英語は得意で成績的にも問題ありませんでした。
また、歴史的なこと・社会事象的なこと、科学的なことに関してとにかく好奇心だけは非常に旺盛で、授業中も授業を聞かずに資料集を読み耽っていたり、休み時間に資料集を読んで楽しんだり、という状態だったのに加え、記憶力に優れるため覚えて済む科目は楽にこなしていました。
問題は論理の組み立てが不可欠な、数学や理科の第1分野です。「論理の組み立て」というと大変なことのように聞こえますが、息子が立ち止まってしまうのは、5歳児でも簡単に分かるような「論理」です。例えば「5㎝の棒Aと7㎝の棒Bがあります。どちらの棒がどれだけ長いでしょう。」というような設問に対して答えを出すための論理の組み立てができないのです。
もちろん「7-5=2」の計算はできますが、先の設問とこの式との関連づけができないようでした。
そんな頭の構造の息子が、成績が下がったとはいえ中学の数学のテストで平均点を上回るような成績をとっていたことに逆に私は驚きました。おそらく、得意な記憶力を使って習った例題の中から「問題のやり方」を引っ張り出して当てはめて、ということをやっていたのでしょう。
とにかく、高校の受験勉強に迫られて、私としては彼のこの頭の構造の改築に取り組みました。
受験に間に合ったかどうかは分かりませんが、リハビリのように執拗に繰り返すうち、ある程度の効果が認められるようになってきた気がしています。
← もくじに戻る
今後継続してレポートさせていただきます。
← もくじに戻る